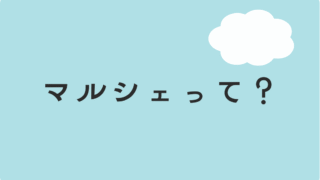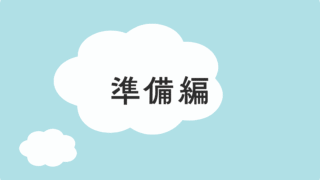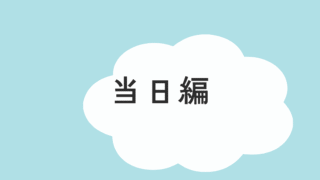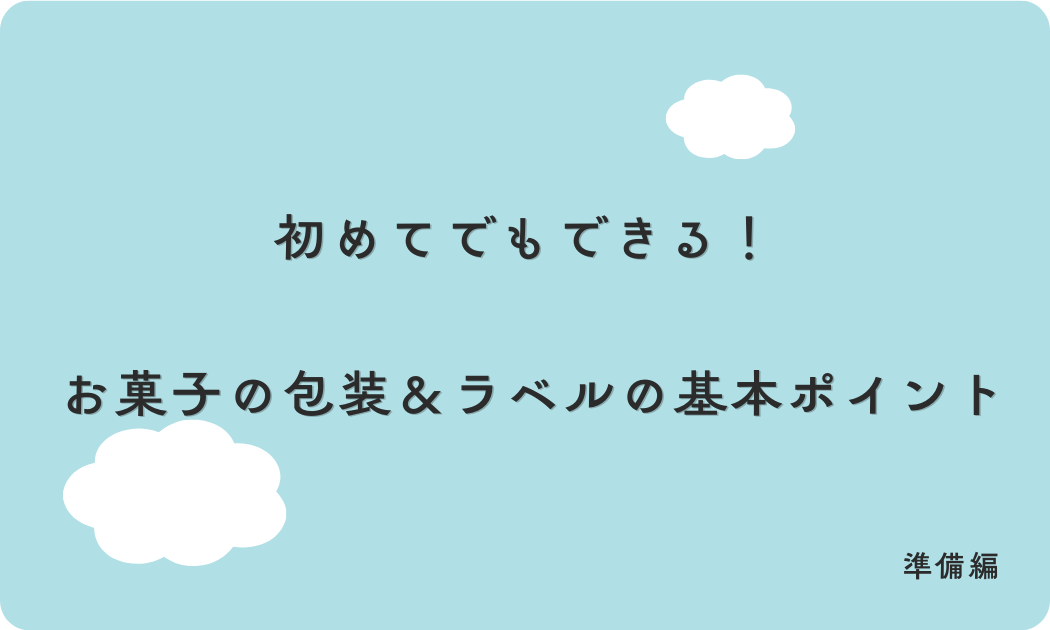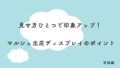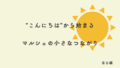マルシェに出店するとき、お菓子そのものの味はもちろん大事ですが、見た目の印象や使い勝手の良さも同じくらいに重要です。包装やラベル、デザインの工夫ひとつで、「手に取ってみたい」「贈り物にしたい」と思ってもらえる確率がぐっと上がります。
この記事では、初めてのマルシェ出店で迷わず一歩踏み出せるように、焼菓子の包装・ラベル・デザインの基本をまとめました。
※記事内に商品プロモーションを含む場合があります
【包装編】見た目も機能も大事!お菓子の“魅せる”包装の基本
1. 包装は「売れ方」を左右する
マルシェでは、お菓子の“第一印象”は包装で決まるといっても過言ではありません。
同じクッキーでも、袋に入っているだけのものと、ちょっと可愛くラッピングされているものでは、手に取られる回数が全然違います。
でも、見た目ばかりにこだわると原価が上がったり、使い勝手が悪かったり…
「見た目」「機能」「コスト」のバランスを意識することが大切です。
2. 基本の包装アイテム
① OPP袋(透明袋)
- メリット:中身が見える、コストが低い、どんなお菓子にも合わせやすい
- デメリット:湿気・酸素遮断性がない場合がある
- おすすめ用途:クッキー、マドレーヌ、パウンドケーキなど
② ガゼット袋/合掌袋など
- メリット:ガスバリア素材の袋と脱酸素剤や乾燥剤を併用することで、食品の酸化・湿気・変色・風味劣化を抑えることができます
- デメリット:透明度やコスト、湿気・酸素遮断性などの機能性は製品によって特性が異なる
- おすすめ用途:クッキー、マドレーヌ、パウンドケーキなど
③ 脱酸素剤・乾燥剤
- メリット:賞味期限を延ばせる、品質保持
- デメリット:コストがかかる
- おすすめ用途:焼き菓子全般、遠方への発送品等
④ 紙袋・紙箱
- メリット:高級感が出せる
- デメリット:単価が高め、在庫の管理が必要
- おすすめ用途:ギフトセット、贈答用
⑤ シール・リボン・タグ
- メリット:ちょっとしたアレンジで見た目アップ
- デメリット:パーツの管理、ラッピングの時間・手間がかかる
- おすすめ用途:イベント限定商品やギフト向け商品
⑥ シーラー
プラスチックフィルム包材やポリ袋の開口部を密封するための機械のこと
- メリット:袋を密封することができる、鮮度保持や安全・品質管理ができる
- デメリット:導入にコストがかかる。置くスペースが必要
- 必要用途: 密封したい場合。脱酸素剤・乾燥剤を使用する時
3. 機能性で選ぶポイント
- 衛生面・鮮度保持:脱酸素剤や乾燥剤は正しい使用方法で使い、シーラーでしっかり封をする
- 開けやすさと見た目:お客さんが開けやすい袋・パッケージか確認
- 在庫管理・コスト:サイズや色等、種類を増やしすぎない方がベター
4. 実体験からのアドバイス
○ お菓子を直接入れる袋は、シンプルなものを選んでできる限り、統一するのがオススメ。
○ 資材は、たくさん種類を使うとその分、在庫やコストが増えて管理が大変になります。
○ おしゃれでかわいいラッピングは目にとまりやすい一方、手間がかかりがち。
お客様に喜んでもらえる商品作りは、「作業効率」や「持ち運びのしやすさ」等、バランスをとりながら決めることも大切です。
5. おすすめの購入
初心者からプロまで幅広く支持される、豊富な品揃えと使いやすい通販サイトが魅力
日本最大級の製菓・製パン材料販売会社。プロも認める品質と豊富な品揃え
シモジマ/パッケージプラザ:オンラインショップだけでなく、全国各地に店舗があるのが魅力。実際に見て選ぶことができる安心感
6. 包装編|まとめ
包装は「ただ包むだけ」じゃなく、商品の魅力を引き出す大切な要素です。衛生・安全面はもちろんですが、デザインやラベルとの相性を考えながら、自分らしい“魅せ方”を見つけていきましょう。
【ラベル編】見やすく、必要な情報をしっかりと
1. 食品表示ラベルに載せる基本情報
食品表示ラベルは、安全に正しく食品を選択できるようにするための「食品表示法」で表示が義務付けられているラベルです。
▪️ 主な記載項目
- 名称:一般的な名称を記載
- 原材料名:使用した原料を重量が多い順に記載。アレルゲンも表記
- 添加物:物質名・用途を明確に区分し、原材料とは分けて記載(原材料の後ろに/添加物と記載する場合も)
- 原料原産地名:主な原材料の産地を記載
- 内容量:gや個数などで記載
- 消費/賞味期限:急速に劣化するものは消費期限、それ以外は賞味期限
- 保存方法:推奨する保管方法
- 製造者/販売者:名称・住所の記載は必須
- 栄養成分表示:熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量など。加工食品は義務付け。(「推定値」等の文言を記載する)
注意点※ 無添加や有機などの表記に関して、消費者に誤解等を与えないよう規定が設けられています。ガイドラインに沿って表記することが求められます
▪️ アレルゲン表示が必要な食材 (2025.4現在)
【義務】特定原材料 8 品目 えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
【推奨】特定原材料に準ずるもの 20 品目 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、 ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン
ここでは、2025年8月現在の資料をもとに「焼菓子販売を想定して」ざっくりと説明していますので、最新ルール・詳細は消費者庁や関連機関のガイドラインを参照することが重要です。
参考:消費者庁「早わかり食品表示ガイド」
2. ラベルの作り方
① 自宅で手作り
- ラベルシールを購入して、家庭用プリンターで印刷
パソコンとプリンタがあれば初期費用を抑えられます◎ - Canvaなどの無料ツールで簡単に作れます。(Canvaはテンプレートあり!)
- Excel等を使用して自作することも可能
② ネット印刷を利用
- プロ仕上がりで耐水性も◎
- テンプレートに文字を打ち込むだけで完成するサービスもあります
③ 専用のラベルプリンタを使用
- ラベルプリンタ、導入コストはかかりますが、ラベルを1枚単位でプリントできて無駄が出にくい良さもあります。使用頻度が高く、長く続けていく場合はあると便利な一台。低価格なものから、高機能高価格なものまでさまざま。
↓↓ ぐらが使用しているラベルプリンタはこれ

基本は、食品表示ラベル専用のプリンタとしてパソコンと組み合わせて使っています。やはり、1枚からプリントできることと、ちょっとした内容の変更にもすぐ対応できるのが強み。卸先のバーコード印字の要望にも対応できて便利。
スマホやタブレット専用のアプリと接続して、編集・作成・印刷も可能です!
4. よくある失敗と対策
●ラベルが大きすぎてお菓子のパッケージとのバランスが悪い
→ パッケージを決めたら、ラベルのサイズを他店の商品などを参考にある程度決めておく
→ 量産前に必ずひとつだけ試作で完成まで作ってみる
●文字が小さすぎて読めない
→ 表示に用いる文字のサイズは、8ポイント以上推奨。
ただし表示可能面積が小さいものは、5.5 ポイントまでの活字を使用
ラベル用紙にプリントする前にまずは普通紙に試し刷りしてしっかり読めるか確認しておく
プリント時に“解像度”や“品質”の設定を確認しておく
●インクがにじむ
→耐水ラベルやレーザープリンタを検討
●ラベルが剥がれる
→耐水・強粘着タイプにする
5. まず揃えておきたい基本アイテム|自作する場合
- パソコン・プリンター
- ラベル用紙(A-oneが有名で種類も豊富)
- 試し刷り用の普通紙(ラベル用紙へのプリントミスを減らすため)
- シンプルで見やすいテンプレート(Canva等)
【デザイン編】“らしさ”を見せるデザインの基本

1. デザインの役割は「覚えてもらうこと」
マルシェで並ぶお菓子は、見た目の印象がとても大切です。
「どこのお菓子だったかな?」と後から思い出してもらえるよう、統一感とわかりやすさを意識したデザインにするのがおすすめです。
2. 統一感を出す3つのポイント
① カラーパレットを決める
- ナチュラル系(ベージュ・ブラウン・ホワイト)
- ポップ系(パステルカラー)
- 高級感(モノトーン+差し色ゴールド)
色を2〜3色以内に絞るだけで“まとまり感”が生まれます。
② フォントを固定する
ロゴ制作までいかなくても、店名を常に同じフォントで印字したシールを貼るだけでも、”このお店の商品感” まとまりがでやすくなります。
③ ロゴやマークを活用
小さなシールやタグでもロゴがあるだけで“ブランド感”がぐっとアップします。
デザイナーに作ってもらうのも、もちろん良いですが、
最初は無料ツール(Canvaなど)でシンプルなロゴを自作することも可能。
イメージに合うフォント+色を ロゴシールとしてプリントしてお菓子の包装に貼るだけでも雰囲気がでます!
4. 実体験からのヒント
おしゃれなロゴに憧れますが、”読みやすさ” や “わかりやすさ”は、とても大切。
店名の色とフォントを統一してプリントしたシールを貼るだけでも覚えてもらいやすくなります。
はじめは、凝りすぎない方が◎ シンプルすぎるくらいが丁度良かったりします。
ロゴは、お店の顔でもあるので頻繁に変えることはオススメできませんが、出店を重ねる中でより良いものに変更してもOK。お菓子の包装のデザイン、初出店では完璧を目指そうとせず、自分で出来る範囲で試してみるのも◎
5. すぐ試せる無料ツール
- Canva:テンプレート豊富で初心者でも使いやすい
- Adobe Express:より細かいデザイン調整が可能
まとめ
お菓子販売における 包装編・ラベル編・デザイン編、いかがでしたでしょうか?
どんな形がいいか悩み迷うところでありながら、少しでも形になると、商品らしさやブランド感がアップしてワクワクするところでもあります。はじめから、完璧にしなければ!と考えると詰まって先に進めなくなってしまうもの。初心者の時期は、やりながら変えていくくらいの気持ちでも大丈夫。だんだん自分の形ができていきます。
これからの出店に少しでも参考になれば嬉しいです
👉️ 準備編 top